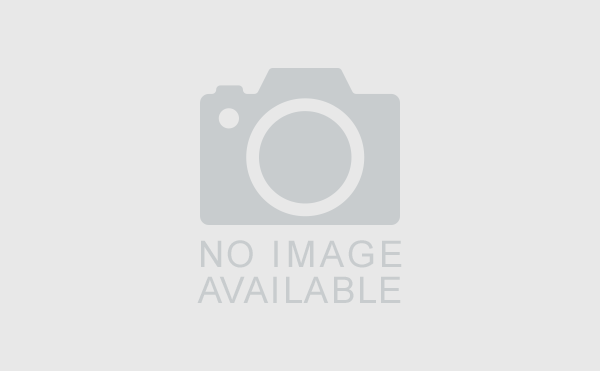人材紹介企画 「コーキョーメグリ」vol.6【小野寺 崇】


小野寺 崇さん
宮城県登米市(議会事務局)
-聴く人・書く人-
鈴木 克典(パブリシンク)
鈴木 克典 | Public Platform (public-platform.jp)

ICカードやQRチケットの普及で肩身の狭い切符。でも東京駅には、そのアナログなチケットを持っている人だけが、東海道新幹線から東北新幹線への乗り換え専用改札を利用できる。混み合う在来線コンコースを通らずホームヘ辿り着けるのだから、アナログも捨てたもんぢゃないな。
くりこま高原駅が最寄り駅。もう乗り換えは面倒なので、停車駅が多いが「やまびこ」に乗車。それにしても、夏休みに突入したばかりだからか、最近の「北に帰る人の群れ」は、意外と賑々しい。仙台を過ぎると、窓と杜との距離が近くなる。トンネルの合間には、蒼く滑らかな田園風景が広がり、稲の葉が風に棚引かなければ、ゴルフ場と見紛う。減速したということは、あのロケ地は近いぞ。

地元で地方公務員になろうと思った理由や、入庁後の勤務経験などを教えていただけますか?
本当に正直なところ、特に登米への愛着が深かったわけではなくて、合併前の迫町役場が近いし、公務員は安定してると思ったからなんですよね。
国際交流事業を担当した後、財政課を3年経験したタイミングで合併し、登米市職員の身分になりました。そこで広報紙を作っている年度途中で固定資産担当に。その後、2年間の宮城県庁派遣と4年ずつの人事課とブランド戦略室を経て、シティプロモーションを5年ほど担当しました。
いろいろ渡り歩いて、現在は議会事務局にいます。
生粋の登米っ子は、外に出たいと思わなかったのですか?
近いからと役場を受験した割に、内心では地元から出たかったと思います。そんな想いとは裏腹に、配属先は庁舎すら離れる機会が少ない、内向きな部署ばかりでした。足元を見る時間はあっても、何も見ていなかった。そう自覚したきっかけは、やはり合併ですね。勤務地は役場のままでも、他の地域からの同僚とも仕事をする。何気ない会話の中でも、自分は「地元を知らない」と感じました。
その感覚が「恥ずかしさ」に変わったのは、県庁に派遣された時でした。他自治体からの派遣職員に「登米に行ってみたい」と言われても、どこをお勧めしたらいいのかが分からない。でもそれは、自分の勝手な諦めで何も無いと思い込んでいただけであって、調べるほどに色々あるという認識に変わっていきました。
かつて地元愛はさほど深くは無かったそうですが、登米を好きになり始めた一番のターニングポイントは何ですか?
ブランド戦略室で、農家さんと向き合ったことですね。農業について何も知らない私に、皆さんすごく優しくて。
仕事を教えてもらう中で、登米っていいなと実感したし、人の温かさが身に沁みました。恥ずかしがり屋でも、足しげく通って笑顔で挨拶すると、次第に心を開いてくれる。口数が少なくても、地元愛を感じさせる人々と触れ合えたことは、非常に大きな転機になりました。その繋がりは、後々のプロモーションも助けてくれた、まさに財産です。


もはやNHKの連続テレビ小説「おかえりモネ」を呼び込んだ立役者として有名ですが、PRや営業が実ったのですか?
いいえ、たまたまNHKが撮影場所を探していたんです。ちょうど観光シティプロモーション課ができるタイミングでしたが、ロケツーリズムは道半ばでした。だからこそ、チャンスだと感じたんですよね。放送されれば、映像という住民の目に見えやすい形でPRの成果を示せるから。
予想どおり、放映の前後では登米のイメージに変化が起こりました。映える画面を観た全国の人がステキと褒めてくれて、それを聞いた地元の皆さんが喜んでくれる。愛着づくりとしては、一番いい効果が生まれました。
予想していなかったのは、私自身の変化かもしれない。営業して掴んだロケではなかった反面、丁寧な黒子に徹しました。100人以上の制作スタッフとの窓口は1人。事前に200カ所以上をロケハンしたり、本番のロケにも市内外を問わず1カ月ほど同行したりと、結構大変な仕事でした。でも、だからこそスタッフとの信頼関係を築けたし、住民の皆さんにも喜んでもらえました。裏方を支え遂げたという自負は自信になり、いつの間にか私の地元愛がどんどん深まっていったんです。そうでなければ伝統行事である「登米能」にも絶対に関わらなかったと思います。
改めて、他の自治体にシェアできる小野寺さんの強みは?
ロケ対応なら、ドラマ撮影をどう盛り上げるかを伝えられるのが、強みかなと思います。やらずに後悔しないためには何をやるべきかとか、スタッフとの距離をどう保つかとか。そしてロケツーリズムなら、来訪者を楽しませ喜ばせるマインドを大切にした、観光の考え方とか。あまりに貴重な経験だったから、自分の中だけに留めておかずに、広く伝えていきたいですね…恩返しの意味でも。
議会に異動したとはいえ、観てもらうプロモーションで終わらせず、ロケ地のレガシーを守りつつ、人々の交流を生み続けたいと思っています。来訪者の感動が住民に伝わることは証明済みです。そこから先、まちを自ら盛り上げ「登米で暮らせて良かった」みたいな実感を抱ける人を、どうしたら増やせるのか。未だもがいている一人として、担当者の苦労に共感できるのも、強みかもしれませんw
最後に、小野寺さんにとっての「公共」とは?
お互いさまの意識ですかね。誰かの役に立つ、そんな情を持ち合うことかなと思います。行政ならば、助けるべき人に手当てできる職員でなければいけない。変化が著しい世の中で、どうすれば対応できるのか、自ら勉強して考え続けなきゃいけないですよね。思いやり続けるというか、そうすれば悪い方には行かないんじゃないかと。
具体的には、声をかけることに尽きるのかな。どんどん「大丈夫?」って。その時、手を取って一緒に歩くのか、背中を押して送り出すのか、選択肢がありますよね。行政だからといって、引っ張るだけが正解ではない気がするんです。声がけは躊躇せず、でも手を繋ぐタイミングは察する。個への心配りが、お互いさまの始まりですから。

【帰路の車中で想う】
とにかく笑顔。車窓に飛んでいく近景に目が疲れ、ふと遠くの空に視線を移すと、また思い浮かんでしまう笑顔。こんなに印象に残る黒子は、失格かもしれない。
ロケ地の北上川堤防。水と空の青さに感動していると、小野寺さんは隠しっ持っていた素っ気ない紙袋から、まさにそこで撮影されたシーンのA3コピーを取り出し、土手道に何枚も並べてくれた…やられたな。その時、彼の額からアスファルトに滴って、瞬時に蒸発した数粒の汗。美しい景色と同じくらい、大切にしなきゃいけないことに気付かされた。人は、見えない「想い」にも動かされるんだ。
話す人
小野寺 崇(オノデラ シュウ)宮城県登米市議会事務局政策・改革係主査